非認知能力の醸成に大切なこととは?
非認知能力とは
学力テストや知能検査で測定可能な認知能力「ではない」能力で、非認知能力とは社会情動的スキルとも呼ばれており、具体的には、創造性や協働力のような特性や能力[2]などがあげられます。
AIやIT技術が予測を上回る発展を見せ、この先の私たちの働き方にも大きな転換期が訪れるといわれています。未来の働き方に対応するためには、それらの技術を使いこなすことも重要ですが、本当に求められるのは変化に適応できる力かもしれません。
教育でも「生きる力」の醸成が重視されているように、これからのこども達(「こどもが主役」のキッザニアで職業・社会体験をする3歳~15歳のゲストを「こども」と表記します)が自立して社会生活を営んでいくうえでは、自由な発想を持ちながら、自分とは異なる他者と協調していくことが重要になってきます。そのために鍵となるのが「非認知能力」です。
非認知能力がなぜ重要視されているのか?
私たちの知的能力の中で、認知能力以外の力を明らかにする取り組みは、実際には1960年ごろには始まっていました。その後、非認知能力として認識されるようになったこの力は、アメリカの経済学者であるジェームズ・ヘックマン教授が、その重要性を説いた[3]ことで社会的に注目されることになります。
彼は、自身の研究の中で、こども達が将来社会経済的に成功し、ウェルビーイングな生き方を獲得するためには、非認知能力を育成することが重要であると主張しました。
ヘックマン教授によると、人生で成功を収めるためには認知能力だけではなく、幼児期から非認知能力を高めることが重要だということです。非認知能力が、その先の人生に大きく作用することを明らかにしたのです。
なお、「ウェルビーイング」について詳しくは以下の記事をご覧ください。
ウェルビーイングとは?教育で求められることを事例で紹介
学校での取り組み事例
ジェームズ・ヘックマン教授も述べているように、非認知能力の育成は人格の基礎が形成される幼児期が、スタート地点として望ましいといわれています。
日本においても、国立教育政策研究所によって「非認知的(社会情動的)能力」の発達などについて研究が報告される[4]など、関心の高さが伺えます。
また、幼児期から小学生以降の非認知能力育成へ向けた取り組みが、日本全国で行われています。その事例の中から、自己肯定感やリーダーシップを育むと考えられる異学年交流について、小学校での取り組みをいくつか紹介しましょう。
香川県教育委員会が発表している事例[5]では、こども達の交流を軸にした活動が紹介されています。学年を超えたグループをつくり、学校行事の企画や調査学習などを行う取り組みです。異なる年齢のこども達がコミュニケーションを取ることで、相手を理解し良好な人間関係を育成する効果が見られたそうです。
具体的には、「異学年交流学習」という枠組みで6年生と3年生のペア学年を設定し、上の学年が下の学年のこどもに算数を教えるという取り組みが行われています。その際に教える側は教え方を自分で考えるので、大きな学びになることが考えられます。また、その後には、教えたこどもと習ったこどもが「お互いの良さを伝えあう」時間があるため、両方の自尊感情が高まることが期待されます。
他にも、自己肯定感を高めることを目指して、他のこどもの良い行動に気づいたときには、そのことを「思いやりカード」に記入して校内のポストへ投函するという取り組みも実施されています。「思いやりカード」の内容は、昼食時の放送で紹介され、さらに校内に掲出する、という仕組みもできています。こういった仕組みを回していくことにより、こども達の自己肯定感が高まることが期待されます。
ちなみに、こどもが主役の街キッザニアでも、年齢の異なる他者との交流や、ガイド役であるスーパーバイザーとの交流が、こども達の非認知能力を高めるための大切な役割を担っていると考えられます[6]。そうして醸成された非認知能力は、学校生活の中でも活かすことができるのではないでしょうか。

こども達の非認知能力を伸ばすポイント
非認知能力は、日々の生活の中でこども達の成長といっしょに形成されます。毎日の経験や自分の内面から生じる感情など、自分自身とそれを取り巻く環境の中で非認知能力は養われます。
そして、こども達を取り巻く環境をどのようなものにするかについては、大人が大きな役割を担っていると考えられます。そこで、キッザニアが重視している大人が目指したい、こども達への向き合い方について、いくつかご紹介します。
●こども達自身の決定を尊重する
こどもが好きだと感じることや、やってみたいと思ったことは、まず否定せずに尊重する姿勢が重要です。最初は上手にできないこともあるかもしれませんが、興味を持って自分が選んだことを実行するうちに、自己効力感や自己肯定感で満たされるようになるでしょう。
好きなことならすぐ覚えられる、楽しいことなら続けられるという経験は誰にでもあるはずです。一歩踏み出すときに、こども達に自己決定を促すことが大切です。
●こども達の挑戦を積極的に応援する
周囲がこども達のために安全な道を選ぶことは、場合によっては必要かもしれませんが、何かに挑戦する機会を失わせる可能性もあります。損得や価値を考える前に、こども達の挑戦を見守る姿勢が非認知能力の育成につながるのです。「応援するからやってみて」というひと言が、こども達に自信を与えてくれるでしょう。
●こども達が失敗しても否定しない
挑戦と失敗とはセットのようなものなので、もしもこども達が失敗した場合でも、周囲が前向きに受け止めることが大切です。挑戦~失敗というサイクルを否定されると、こども達は挑戦することそのものを恐れるようになるかもしれません。失敗から学べる可能性があることは、こどもも大人も変わりません。
●こども達と周囲との関わりを大事にする
こども達の意思を尊重することは重要ですが、すべてを本人に任せるわけではありません。周囲の仲間とのコミュニケーションは重要であり、ときには相手の意見を尊重して、自分が譲歩する必要もあります。人間には社会性が不可欠なので、大人も含めた周囲との関わりは大切にしなければなりません。
このように、こども達の主体性を尊重することは、キッザニアでの体験に積極的に取り入れられています。キッザニアではこども達が自ら選択して、初めての職業・社会体験に挑戦します。

次のテーマでは、キッザニアと非認知能力との関わりについて紹介しましょう。
キッザニアと非認知能力
VUCAといわれる時代だからこそ、こども達の「生きる力」を育むために、キッザニアでも非認知能力により一層注目しています。ここでは、キッザニアを訪れたご家庭から寄せられた、こども達の変化と成長のエピソードを一部紹介します。
・消極的だったのが、何回か行くようになってから予約を取ったり、自分からスーパーバイザーさんに質問したりできるようになった。
・学校生活において積極的に人前で発言することが増えた。
・日常でも「どうせできない」という考え方をすることがあったが、「とりあえずやってみる」に変化してきたと思う。
これらのエピソードからは、キッザニアでの体験が非認知能力の醸成への一助となる可能性が示唆され、また日常生活における生きる力への広がりが感じられます。ではキッザニアの体験の中で、こども達の非認知能力はどのように育成されるのでしょうか。
キッザニア施設内での取り組み事例
キッザニアでは、施設内でのアクティビティ(仕事やサービス体験)選択や他者とのコミュニケーションを通じてこども達の自立心が高まり、そこから日常生活における非認知能力へポジティブな影響があるという傾向が確認されています[6]。また、アクティビティでは、こども達が達成感を感じられるようなストーリーが存在します。まず、初めて施設を訪れたこども達は、なかなか最初から積極的にアクティビティに参加することができません。そんなときにはスーパーバイザーがさりげなくサポートします。ときにはほかのこども達が声をかけあい、お互いをフォローしてくれることもあります。
実際にアクティビティを体験する場合は、いっしょに体験する仲間と関わり合いながら活動します。ほとんどは初対面同士ですが、活動を通じてお互いを認識し協力関係を築いていきます。こうしていくつかの活動を体験するうちに、こども達の中で自己制御や協調性、社交性や思いやりなどの力が豊かになっていくと考えられます。
キッザニアでは、実社会で目にする職業を体験できます。例えば銀行、病院、ハンバーガーショップなど、身近にある職場とほとんど変わらないリアルな環境になっています。
仕事をすれば当然お給料がもらえますが、キッザニアでは施設内で流通する「キッゾ」という専用通貨でお給料が支払われます。このキッゾは、受け取るだけでは終わりません。
施設内でサービスを受ける立場になったとき、こども達はキッゾで支払いができます。さらに銀行に口座を開いて預金し、ATMで引き出すことも可能です。こうした一連の体験は、楽しみといっしょに、非認知能力である社会的スキルや自己管理スキルの向上が期待されるでしょう。

アクティビティを体験したあとは、スーパーバイザーから活動結果が評価され、こども達がアクティビティの振り返りながら、保護者や先生のもとに戻ります。こども達は1つのことをやり遂げた達成感と、自己肯定感が生まれるでしょう。
キッザニアが2020年11月に実施した調査結果の中で、過去にキッザニアを体験したこども達の保護者へのアンケートによると、主に以下に挙げるような非認知能力の伸長が見られたそうです。
①チャレンジ精神(78%)
②行動力(63%)
③自立心(50%)
④コミュニケーション力(43%)
⑤協調性(39%)
※複数回答で上位5位まで、( )内は回答者の割合
こうしてキッザニアでアクティビティを体験したこども達は、その達成感が日常生活へもポジティブな影響を与える傾向があり、それが非認知能力につながっていくということが考えられます。そのことが、学校でも社会でも、自立心と自信を持った行動につながっていくかもしれません。
なお、キッザニアでの取り組み事例詳細については、以下の資料をご覧ください。
キッザニア白書2021
キッザニアでこども達の非認知能力を育もう
現在多くの学校で、非認知能力を向上させる取り組みが行われています。今回紹介した異学年交流もその一例です。年齢が違う仲間や、大人たちと接することは、こども達の中のさまざまな感情や能力を高め、それが非認知能力の育成にもつながるのです。
このように多種多様な人たちとの交流は、キッザニアでは日常的なことです。こども達は働く側とサービスを受ける側と、両方の立場を体験しながら、さまざまな交流を通じて周囲と良好な関係を構築します。こども同士ばかりでなく、「職場のちょっと上の先輩」という斜めの関係性であるスーパーバイザーとのコミュニケーションも数多くあります。

またキッザニアでは、こども達は常に挑戦と失敗を繰り返しますが、それを否定されることはありません。やってみたいことを見つけて挑戦し、成功すれば達成感と自己肯定感を得ることができます。成功しても失敗しても、そこでこども達は1つ成長するはずです。
キッザニアは楽しみながら学べる場です。私たちにできるのは、自ら進んで行動するこども達をサポートすることです。これからもキッザニアは、それぞれのこども達の挑戦や成功を支える場であり続け、そこで成長するこども達といっしょに、次世代の社会づくりに貢献したいと考えています。
キッザニアの取り組みと施設内での活動について、詳しくは以下をご覧ください。
資料ダウンロード
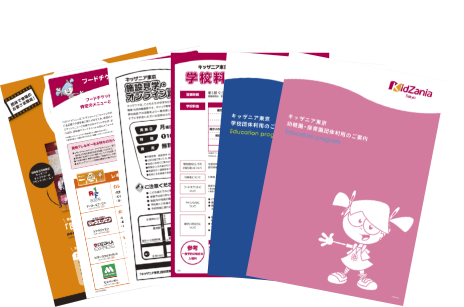
- OECD (2015), Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, pp.34
- 日本生涯学習総合研究所(2020)『「非認知能力」の概念に関する考察Ⅱ~「非認知能力」の要素における関連性の観点から ~<改訂版>』
- ヘックマン,J.J.(2015)『幼児教育の経済学』古草秀子訳, 東洋経済新報社
- 国立教育政策研究所(2017)「非認知的(社会情緒的)能力の発達と科学的検討手法についての研究に関する報告書」
- 香川県教育委員会(2021)『非認知スキル向上プログラム 学校・家庭・地域で子どもの夢を応援しよう』
- KCJ GROUP 株式会社(2021)『キッザニア白書2021』
【監修者紹介】立石 慎治 先生
(筑波大学 図書館情報メディア系 助教)
立石先生の詳しいご紹介はこちらです。

