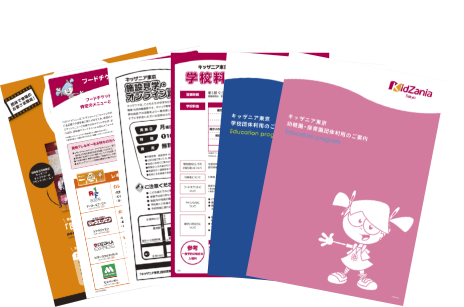こども達の可能性を広げるICT教育の方法とは
ICT教育が登場する前の教育現場では、それぞれのこども達の学力に合わせた学習や、個性を伸ばすための取り組みを実践することは難しい問題でした。思考方法や理解の仕方は個々に異なり、同じプロセスで学習を進めると、どうしても結果にギャップが生じてしまいます。それに対して適切なサポートをしないと、こども達が特定の教科に対して苦手意識を持ったり、勉強そのものが嫌いになったりする恐れもあります。
ICT教育の導入により広がる可能性の1つが、前述した課題を効果的に解消することです。そしてもう1つの重要なポイントは、これからの社会で必要になる知識や技能・スキルを学ぶことです。さらにICT教育では、それぞれのこどもに最適な学習プロセスを選ぶこともできます。
今回のコラムでは、技術・情報教育の専門家である岩田 亮 先生に、ICT教育の具体的な手法を紹介していただきます。導入を検討、もしくは実践する際の参考にしてください。
【執筆・監修者紹介】岩田 亮 先生
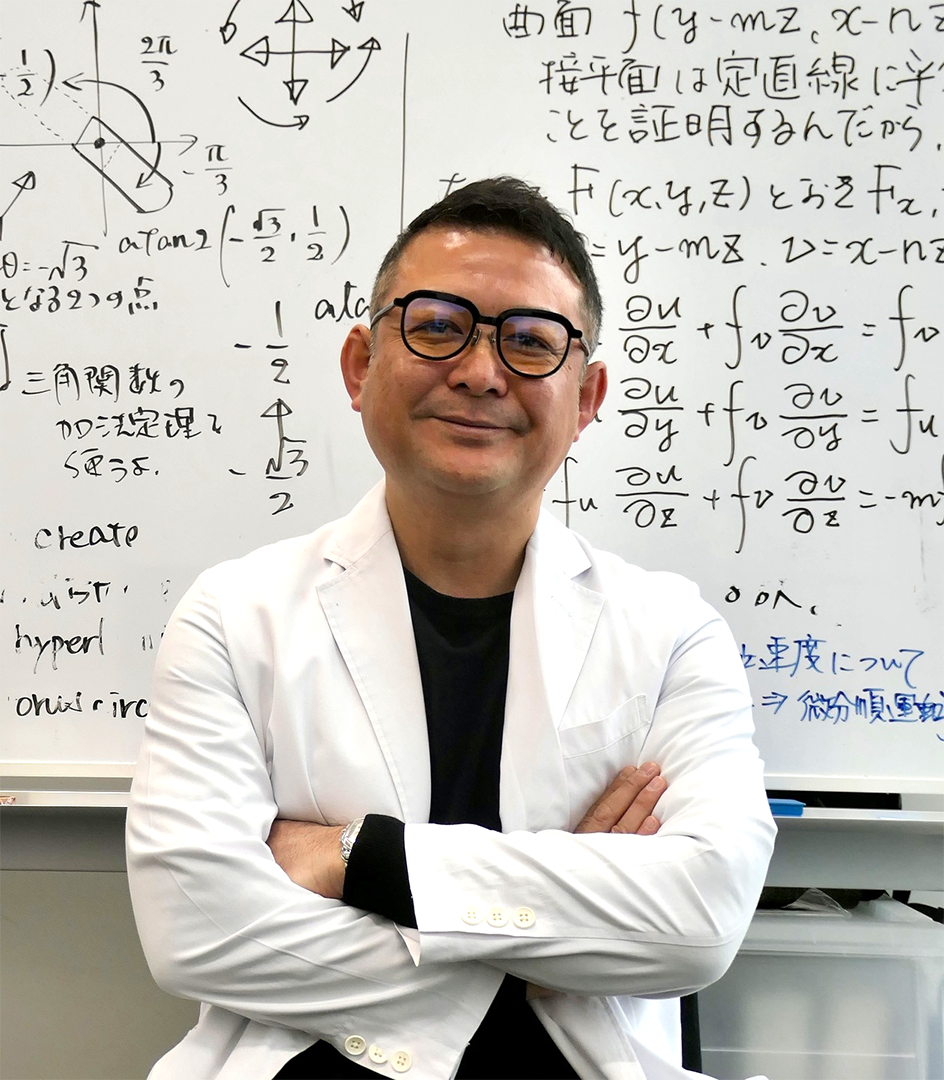
芝浦工業大学附属中学高等学校 学年主任(技術・情報科)。
関わった著書に『PBLのカリキュラムデザイン』『はじめてのロボコンにチャレンジ』等。
研究分野は『指導方法と教育教材の開発に着目した制御系プログラミング教育』。
2018年より非常勤講師として国立大学の教職課程『情報教育法Ⅰ』を担当。
ICT教育の可能性と課題
デジタル化が急速に進展する現代において、教育のあり方も大きく変化しています。その中心にあるのが、情報通信技術(ICT)を活用した教育、すなわちICT教育です。タブレット端末やパソコン、そしてインターネットの普及により、学習の場は教室から世界へと広がり、従来の受動的な学習から、能動的で創造的な学習へとシフトしつつあります。
ICT教育がもたらす最大のメリットは、学習の個別化でしょう。一人ひとりの学習進度や興味関心に合わせて、最適な学習内容や学習方法を提供することが可能になります。これにより、生徒は自分のペースで学習を進め、得意な分野を深めたり、苦手な部分を克服したりすることができます。また、学習の多様化も大きな特徴です。ゲームや動画、シミュレーションなど、多様な教材を活用することで、学習はより楽しく、そして効果的になります。さらに、ICTは、協働学習を促進します。オンライン上で世界中の学生と繋がり、共同でプロジェクトを進めることで、コミュニケーション能力やグローバルな視点が養われます。
しかし、ICT教育の導入には、いくつかの課題も存在します。デジタルデバイドは、最も大きな課題の1つです。家庭環境によって、ICT機器へのアクセスやインターネット環境に大きな差が生じ、教育の機会が不平等になる可能性があります。また、前回のコラムで書きましたが、特にネットリテラシーや情報モラル教育は重要です。インターネットの安全な利用方法や著作権に関する知識を身につけることは、デジタル社会を生きるうえで不可欠です。さらに、教員の負担増も懸念されています。ICT機器の操作や新しい教材の開発、そして生徒一人ひとりの学習状況を把握することは、教員にとって大きな負担となる可能性があります。
ICT教育は、教育の質向上に大きく貢献する一方で、その普及には、デジタルデバイドの解消、情報モラル教育の充実、教員のサポート体制の強化など、さまざまな課題を克服していく必要があります。政府や学校、そして家庭が協力し、ICT教育を効果的に推進していくことが求められています。

ICTで深まる学び:こども達の可能性を広げる多様な手法
さて、ICT教育は、単にパソコンやタブレットを使うだけでなく、こども達の学びを深め、可能性を広げるための多様な手法を提供します。ここでは、これからICT教育を始めよう!あるいは興味がある、という小学校、あるいは中学校の先生方に向けて、ICT教育の代表的な種類と、それぞれの特長について詳しくご紹介します。自らの経験値より、指導方法があまり複雑ではなく、児童・生徒の皆さんがスムーズに活用できるツールを記載してみましたので、ぜひご活用ください。
※一部、個人で活用できないツールもあります。
1)デジタル教科書・教材で、学びをもっと楽しく!
紙の教科書に代わって、動画や音声、インタラクティブな要素が満載のデジタル教科書が登場しました。まるでゲームをしているように、こども達は楽しみながら学習を進めることができます。図やグラフを拡大したり、動画を繰り返し見たりすることで、より理解を深めることができるでしょう。
<ツール例>
①Google Classroom: 課題の配布、提出、フィードバックを一元管理。
②Kahoot!: クイズゲーム形式で知識定着を促す。
2)学習管理システムで、一人ひとりの成長をサポート!
学習管理システムは、こども達の学習進度や成績を細かく記録し、先生方は一人ひとりの状況を把握することができます。これにより、苦手なところを重点的に指導したり、得意なところをさらに伸ばしたりと、きめ細やかな指導が可能になります。
<ツール例>
①Google Classroom: 学習進度や成績を管理。
②Classi: 大規模な学習管理に適している。
3)オンライン学習で、いつでもどこでも学びを!
インターネットに接続できる環境さえあれば、いつでもどこでも学習できるオンライン学習プラットフォームがあります。動画講義やクイズ、ゲーム形式の学習など、さまざまなコンテンツが用意されており、こども達は自分の興味に合わせて自由に学習を進めることができます。
<ツール例>
①YouTube: 教育動画が豊富。
②Progate: プログラミングの入門など基礎から学べる。
4)プログラミングで、未来を創る力を育もう!:活用できる教材をDLできます
プログラミング教育は、論理的な思考力や問題解決能力を養うために欠かせません。ブロックを組み合わせてプログラミングをするように、こどもでも簡単に楽しく学ぶことができます。将来、どんな仕事をするにしても、プログラミングの考え方は必ず役に立つでしょう。ここでは、特に操作が易しく活用範囲の広いScratchについて、詳しくご説明します。
<ツール例>
①Scratchの主な特徴は、以下の通りです。
視覚的なプログラミング:プログラムの命令が「ブロック」として表示され、ユーザーはそれをドラッグ&ドロップして組み合わせます。
学習と創造性:こども達はゲーム、アニメーション、インタラクティブな物語などをつくりながら、プログラミングの基本的な概念(条件分岐、繰り返し、変数など)を学びます。
オンラインコミュニティ:作成した作品をScratchのウェブサイトにアップロードして、他のユーザーとの共有や、フィードバックを受け取ることができます。また、他のユーザーのプロジェクトを見て学び、インスピレーションを得ることもできます。
Scratchは、プログラミングをはじめて学ぶこども達に優しく設計されており、直感的に操作できます。
以下は、Scratch以外のプログラミングツールです。
②Viscuit: 図形を動かすことで、プログラミングの概念を学ぶ。
③Micro:bit: 小型コンピューターで、さまざまなセンサーやアクチュエーターを制御できる。
教材ダウンロード
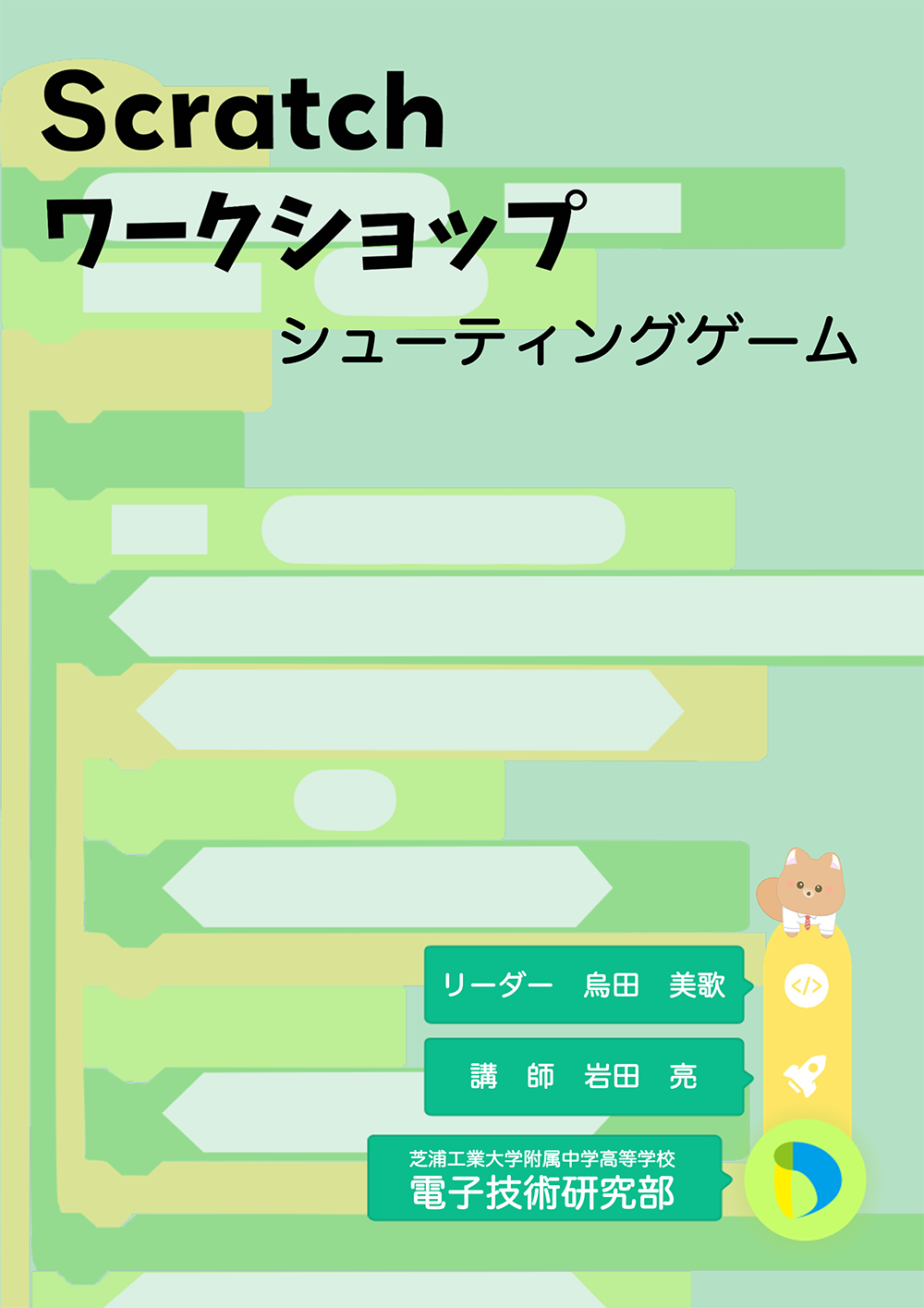
5)AIで、一人ひとりに最適な学習を!
人工知能(AI)を活用することで、一人ひとりのこどもに合った学習プランを作成することができます。AIは、こどもの学習データを分析し、苦手なところを重点的に学習できるような問題を出したり、興味のある分野の情報を提供したりします。
<ツール例>
①Qubena(キュビナ): 学習eポータル+AI型教材による学習内容の自動生成。※個人活用不可
②スタディサプリ:オンライン学習サービスで、AIが学習履歴を分析し、個別の学習プランを提案。※個人活用不可
6)VR/ARで、新しい世界へ飛び込もう!
仮想現実(VR)や拡張現実(AR)を使って、歴史の現場を体験したり、宇宙を旅したりすることができます。まるでその場にいるかのような臨場感あふれる体験は、こども達の学習意欲を刺激し、記憶に残りやすい学習体験を提供します。
<ツール例>
①Google Expeditions: 仮想現実で世界中の場所を探索できる。
②CoSpaces Edu: AR/VRコンテンツを簡単に作成できる。
7)IoTで、身の回りの世界を学ぼう!
身の回りのモノがインターネットに繋がるIoTを活用することで、温度や湿度などのデータを収集し、グラフを作成したり、ロボットを動かしたりすることができます。これにより、こども達は、科学的な思考力や問題解決能力を養うことができます。
<ツール例>
①micro:bit: さまざまなセンサーやアクチュエーターを制御できる。
②Raspberry Pi: 小型コンピューターで、IoTデバイスを作成できる。

ここでご紹介した以外にも、役立つICTツールはたくさんありますが、まずは最初の一歩として手に取っていただきたいものを並べてみました。ICT教育は「少し敷居が高い」と思われる先生や「細かそう」と感じてすぐに手が出ない児童・生徒もいると思います。しかし、プログラミングを例に考えると、いくらでもトライ&エラーが許される世界です。間違ってやり直すの繰り返しを経験することで、最終的に自分の思ったものが出来上がる楽しみは特別です。さらに、言語があまり関係ないフィールドなので、世界を目指して自分の、あるいはチームの作品を制作することも可能です。誰でも始めることができて、その先が世界へ繋がるICTの世界へ、ぜひ児童・生徒の皆さんをいざなってみてください。
日々の授業にICT教育を取り入れよう
ここまで岩田先生に、ICT教育を実践する7つの手法と、さまざまなツールを紹介していただきました。まずは手軽に始められることからチャレンジしてみて、こども達といっしょに成功と失敗体験を積み重ねることをおすすめします。
実際にICT教育を実践する場合には、最初から複雑な取り組みを計画するのではなく、ICTの基本を少しずつマスターしながら、1歩ずつステップアップすることが大切だと考えられています。ツールを活用する場合にも簡単なものから始め、徐々に高度なツールに挑戦すると同時に、なるべく多種多様なツールに触れることも重要なポイントだと言えます。
「こどもが主役の街」キッザニアでも、ICT教育に繋がる各種体験を提供しています。
キッザニアではゲームクリエイターとしてゲームを完成させるアクティビティや、自分の手で組み立てるパソコン工場の体験もあります。ほかにも多くのアクティビティで、情報通信などに関わるテクノロジーに触れることができます。
また、スマートフォンやタブレットから参加できる「キッザニア オンラインカレッジ」では、AIエバンジェリストなどのICT教育に関するコンテンツもあり、自宅にいながらキッザニアの活動を体験したり、ワークショップに参加したりできます。今後コンテンツがさらに充実する予定ですが、これもICT教育の一環といえるでしょう。
岩田先生はICT教育が特別なものではなく、トライ&エラーはつきものであり、間違ってもやり直すことができる点を強調されていました。それはキッザニアでの体験も同じです。これからの社会で活躍するこども達のためにも、キッザニアは体験を通じて生きる力を育む場であり続けるとともに、こども達といっしょに次世代の社会づくりに貢献したいと願っています。
キッザニアの取り組みと施設内での活動について、詳しくは以下の資料をご覧ください。
資料ダウンロード