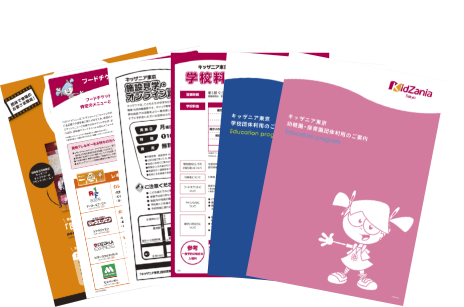こども達へのネットリテラシー教育の重要性と有効な取り組みを解説
後半ではキッザニアでの取り組みについてもご紹介しております。あわせてご覧ください。
ICT教育とネットリテラシー教育
「こども達の生きる力を育む」ことは、キッザニアの重要なテーマの1つです。文部科学省の新学習指導要領でも、「生きる力」を基本理念に掲げています。
現代社会は新しいテクノロジーの浸透により、大きな変革の時期を迎えることになりました。これからの社会を担うこども達は、日常的に最新技術と向き合わなければなりません。そのために必要とされる「生きる力」として、小・中学校でも情報通信技術(Information & Communications Technology)を扱うICT教育が実施されているのです。
政府が推進するICT教育では、「トリプルA」として以下の3つをテーマに挙げています。
・Active:学びを活性化する
・Adaptive:学びを最適化する
・Assistive:学びを支援する
これら3つをベースにして、こども達の学びの可能性を広げ、生きる力の育成を図ることがICT教育を実践する目的だといえます。
もちろん、現代のこども達は幼いうちからデジタル機器に親しんでいるため、大人顔負けのデジタルスキルを身につけています。学校でもICT教育を受けることにより、さらにスキルに磨きがかかることになるでしょう。インターネットの利用も日常生活の一部になり、こども達は日々新しい知識を吸収しながら成長します。
さらに、今後のICT教育ではクラウドシステムの活用が本格化すると同時に、AIの利用が一般的になると考えられます。今までの教育からは想像できないほど大量の情報を、これまでとはまったく異なる方法で扱うことが、教える側と教えられる側双方にとって必要になるかもしれません。
ただし、ICT教育を拡充する上では、常に課題とリスクが伴うことも事実です。これから社会経験を積むこども達にとって、大量の情報の中から正しいものと間違ったものを判別することは容易ではありません。不正な情報にアクセスしてしまい、自分では対処できなくなる恐れもあります。
そこで今、こども達がインターネットのリスクと安全な利用法を学ぶため、ICT教育と並行して、ネットリテラシー教育を導入することが求められています。ネットリテラシー教育では、情報の中に潜む危険を自ら回避して、正しい情報を自分の力で判断する方法や知識について学ぶことになります。
ここからは、ネットリテラシー教育の必要性や効果的な取り組みについて、岩田 亮 先生に解説していただきます。
【執筆・監修者紹介】岩田 亮 先生
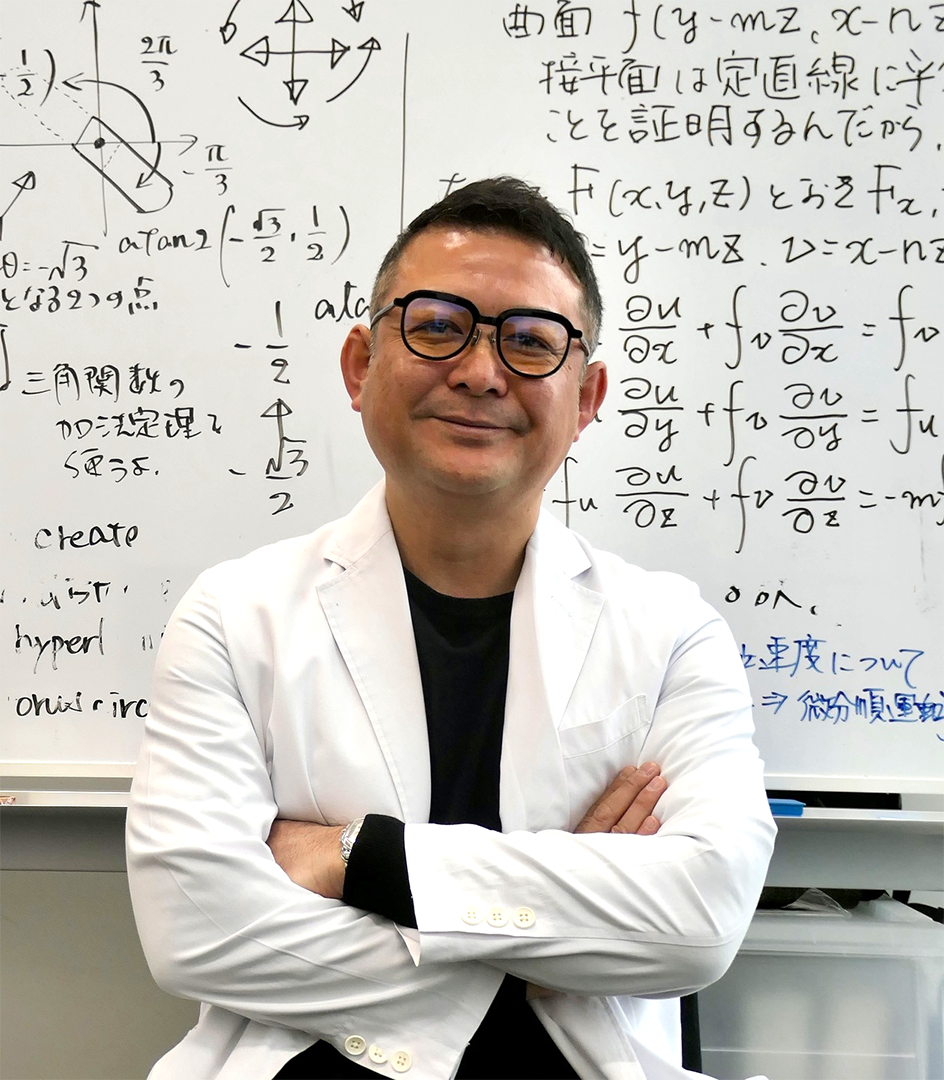
芝浦工業大学附属中学高等学校 教科主任(技術・情報科)。
関わった著書に『PBLのカリキュラムデザイン』『はじめてのロボコンにチャレンジ』等。
研究分野は『指導方法と教育教材の開発に着目した制御系プログラミング教育』。
2018年より非常勤講師として国立大学の教職課程『情報教育法Ⅰ』を担当。
ネットリテラシー教育は、なぜこども達に必要なのか?
今、こども達のネット利用をめぐる問題は、もはや個人の問題ではなく、社会全体が直面する喫緊の課題です。最近の有名人のSNSトラブルのように、一度ネット上に流出した情報は拡散されやすく、取り返しのつかない事態を招くことがあります。総務省の調査[1]によると、中学生の約半数がSNSを利用しており、その中で誹謗中傷を受けた経験を持つこどもも少なくないことが分かっています。
なぜ、このような問題が起きてしまうのでしょうか?それは、こども達がインターネットの危険性や、情報の見極め方を十分に学んでいないからです。インターネットは、便利で楽しいツールであると同時に、使い方を誤れば大きなリスクを伴うものです。特に、こども達は、インターネットの世界で何が起こっているのか、その裏側にあるメカニズムを十分に理解していないため、トラブルに巻き込まれやすいのです。

ネットリテラシー教育は、こども達がインターネットを安全に利用し、そのメリットを最大限に活かせるようにするためのものです。具体的には、情報の見極め方、個人情報の保護、マナーあるコミュニケーションに加え、批判的思考力や問題解決能力を養うことが重要です。「フェイクニュースの見分け方を学ぶ」ワークショップの実施や、シミュレーションゲームを用いた情報セキュリティ教育などが、その一例です。
今、なぜネットリテラシー教育が求められているのでしょうか?それは、ネット上には膨大な情報が溢れており、その真偽を見極めることがますます難しくなっていること、ネット上では匿名でコミュニケーションを取ることができるため、誹謗中傷や嫌がらせが横行しやすい環境になっていること、そして、フィッシング詐欺やハッキングなど、サイバー犯罪が巧妙化しており、こども達も被害に遭うリスクが高まっているからです。
学校、家庭、そして地域社会が連携し、こども達が安全にインターネットを利用できる環境を築くことが求められます。ネットリテラシー教育は、学校教育の一環としてだけでなく、社会全体で継続的に取り組むべき課題です。
ネットリテラシー教育として効果的な4つの取り組み
インターネットは、情報にアクセスしやすくなった一方で、情報の真偽を見極める力が求められる時代になりました。特に若い世代は、インターネットなしでは生活できないほど、デジタルデバイスに慣れ親しんでいます。しかし、その一方で、ネットいじめ、フェイクニュース、プライバシー侵害など、さまざまな問題も発生しています。
まずは、情報の源泉を疑う姿勢を育てることが大切です。インターネット上の情報は、誰でも発信できるため、必ずしも正確な情報とは限りません。情報源がどこなのか、誰が発信しているのか、どのような意図で発信されているのかを冷静に判断する力が求められます。
次に、批判的思考力を養うことが重要です。情報を受け入れるだけでなく、その情報に対して疑問を持ち、多角的な視点から考える力を育む必要があります。そして、得た情報を鵜呑みにせず、自分で確かめる習慣をつけることが大切です。
以下に4つの取り組みを書きたいと思います。
①ネットトラブルに関するニュース記事について一緒に考える
授業の冒頭7分間、私は、SNSでの誹謗中傷や、フィッシング詐欺など、最新のネットトラブルに関するニュース記事をこども達と共有し、一緒に考えます。『どうしたらこのような問題を防げるだろう?』と問いかけ、こども達と一緒に解決策を探る時間を設けています。この取り組みを通して、こども達は、インターネットの危険性を身近に感じるとともに、自ら考え、解決策を提案する力を養っています。例えば、ある授業では、ネットいじめに関するニュース記事をきっかけに、クラス全体で『SNSでの誤解』について話し合い、自分達で「どんな言葉が特に誤解を招くか一覧」を作成しました。
②図書館を活用した学習を取り入れる
図書館は、単に本を借りる場所にとどまらず、多様な情報にアクセスできる貴重な情報源です。図書館員の方々の丁寧なサポートを受けながら、新聞記事、雑誌、データベースなど、さまざまな情報に触れることで、こども達は情報検索のスキルを習得し、情報の真偽を見極め、必要な情報を効果的に収集する能力を養うことができます。また、図書館での読書会や調べ学習を通して、楽しみながら学び、探究心を育むことができます。
③プログラミング教育を行う
プログラミング教育は、単にプログラミングの技術を習得するだけでなく、論理的思考力、問題解決能力、創造性など、これからの社会で必要とされるさまざまな能力を総合的に養うことができます。例えば、プログラミングを通して、自らウェブサイトを作成する経験は、情報の構造やデザインの意図を深く理解するきっかけとなります。また、プログラミング言語のルールを学ぶことは、論理的な思考力を養い、問題解決能力を高めることにつながります。さらに、プログラミングを通して、オリジナルのゲームやアプリを作成することで、創造性を育み、デジタル社会で活躍するための基盤を築くことができます。

④標語コンテストを実施する
ネットリテラシーへの関心を高めるために、標語コンテストの実施は効果的です。今回、私はキッザニアと一緒に、ネットリテラシー教育の啓発ポスターに掲載する標語を考えました。この活動を通して、自分のクラスのこども達に「ネットリテラシーについての標語を考えてみよう!」と提案してみたところ次々とおもしろいアイデアが出されて、こども達は自分の言葉で表現する楽しさを味わうことができました。例えば、『ネットは魔法の杖、使い方はあなた次第!』というような、こどもらしいユニークな標語がたくさん生まれました。
これからのデジタル社会では、ネットリテラシーがますます重要になっています。
個人的には、中学校でネットリテラシーを教科化し、専門のエンジニアによる授業を行うことで、こども達は、情報収集能力、批判的思考力、問題解決能力などを高めることができます。これらは、これからの社会で求められる重要なスキルです。
ネットリテラシー教育を教科化するためには、専門知識を持つ教員の確保や、最新の教材の開発など、さまざまな課題をクリアする必要があります。しかし、これらの課題を克服し、ネットリテラシー教育を充実させることは、こども達の未来を担う上で不可欠な取り組みです。
この教育を充実させることで、こども達は、安全にインターネットを利用し、情報の荒海から必要な情報を的確に選び出す方法を学ぶことができると思います。また、自ら情報を発信し、創造的な活動を行うことも可能になると考えています。
【岩田 亮 先生監修】ネットリテラシー教育に活用できるポスター
こども達が自ら考え、行動し、成長するためには、実体験に基づく学びが大切です。家庭、学校、地域社会など、多様な学びの場を通して、こども達は自ら問題を発見し、解決策を模索する力を養います。

このポスターでは、『自分で』という言葉をキーワードに、こども達が主体的に考え、行動することを促しています。これは、単に知識を詰め込むのではなく、これからのデジタル社会で求められる創造性や問題解決能力を育むことを目指しています。
こども達は、大人から一方的に教えられたことよりも、自ら体験したことを通して、より深く学びます。例えば、歴史の話を聞くだけでは、その時代の人々の気持ちを深く理解することは難しいでしょう。しかし、歴史的な場所に実際に足を運ぶことで、歴史がより身近に感じられ、心に響くものがあるはずです。
教育の目的は、こども達を単に知識で満たすことではなく、自ら考え、判断し、行動できる力を育むことです。そのためには、こども達が自ら体験し、失敗から学び、成長できる環境を提供することが重要と考えられます。
デジタル社会において、こども達はさまざまな情報に囲まれています。インターネットは、便利なツールであると同時に、使い方を誤れば危険なものでもあります。そのため、こども達が安全にインターネットを利用できるよう、ネットリテラシー教育の重要性も高まっています。
このポスターは、こども達が自ら考え、行動するきっかけになればという願いを込めて作成しました。あなたもこどもの頃、何かを体験して大きく成長した経験はありませんか?こども達の成長を応援するためにも、ぜひこのポスターを活用し、こども達と積極的にコミュニケーションを取ってください。
執筆者:岩田 亮 先生
ポスターダウンロード

こども達のネットリテラシーを育み楽しいICT教育を
ネットリテラシー教育を実践する目的は、こども達が正しい情報の見極め方やコミュニケーションの方法について学び、論理的思考力や問題解決能力を養うことです。これは学校教育のみならず、社会全体で向き合うべきテーマだといえるでしょう。
そのための効果的な取り組みとして、記事の中で岩田先生は4つのプランを提案されていました。ポスター制作も加えると、5つの取り組みといえるかもしれません。これらを実践することにより、こども達は情報の扱い方を習得し、普段からリスクに備えることの重要性を学ぶことになります。
岩田先生は、教育の目的として自ら考え、判断し、行動できる力を育むことをあげられておりその力を育むために、こども達が自ら体験し、失敗から学び、成長できる環境を提供することが大切だと述べられています。そして「こどもが主役の街」キッザニアでは、さまざまな種類のアクティビティ(仕事やサービスの体験)を提供しています。これらのアクティビティを通じて、こども達は働く上での基本的なルールを理解し、自分の判断に従って行動するとともに、同じ活動に参加する仲間とのコミュニケーションを構築します。
アクティビティの中でこども達は、多くの情報を自分の頭で整理して、自分の力で判断したり問題解決したりしなければなりません。難しい問題に対処する場合などでは、ほかの参加者やスーパーバイザー(こども達の“ちょっと先輩”という立場で仕事をいっしょにやり遂げるキッザニア体験をサポートするスタッフです。)と協力することで、相手の意思を感じとりコミュニケーションの方法を学びます。最初は難しいと感じたことでも、経験を重ねるうちに少しずつ上手に対応できるようになります。
こうしたプロセスは、ネットリテラシー教育と多くの共通点があります。インターネットを安全に利用するために必要な知識や実践的な方法を学ぶことと、こども達がさまざまな体験を通じて学ぶことには、学び方の本質において類似する部分が多いです。どちらも実際の体験を通じて知識や理解を深める点が特徴です。ほかにもキッザニアには、パソコンやタブレットを用いて職業・社会体験ができるアクティビティが多数あり、施設内でもICTに触れることができます。タブレットは、学びの効果を高める重要なツールとして役立ち、デジタル技術に親しみながら学びを深めることができます。

岩田先生は、ネットリテラシー教育の目的として、こども達がこれからのデジタル社会で求められる創造性や問題解決能力を育むことを目指していると述べられています。そのため、こども達が自分で考え、試行錯誤しながら学んでいくことが重要です。デジタル化社会が進展する中でも、キッザニアは体験を通じて生きる力を育てる場であり続け、こども達とともに次世代の社会づくりに貢献したいと考えています。
キッザニアの取り組みと施設内での活動について、詳しくは以下の資料をご覧ください。
資料ダウンロード