【実践編】アントレプレナーシップ教育のヒント-今日からできる取り組み事例-
アントレプレナーシップ教育は、基礎編でご紹介をした「EDGE-NEXT」などのように、文部科学省による、大学を中心としたアントレプレナーシップ醸成と実践に向けた事業が実施されていますが、その裾野はゆるやかながら広がりを見せています。
例えば東京都では、「小中学生起業家教育プログラム」[1]を開催して、「起業家」を身近なものとしてとらえて、将来のキャリアへの選択肢になるようなワークショップを提供しています。ほかにも、学校単位や自治体単位でさまざまな取り組みが行われています。
しかしながら、実際にアントレプレナーシップ教育を始めようとすると、どのような目標を掲げればよいのか、またどのような内容がこども達にとってわくわくするものとなるのか、まだまだ見えてこないことが数多くあるように思われます。
そこで、実践編では、基礎編に引き続き、さまざまな教育現場でアントレプレナーシップ教育を実践されている大阪公立大学の山田裕美先生から、海外におけるアントレプレナーシップ教育の目的や、大学生の研究事例からわかったこと、さらには小学校での実践例におけるこども達の様子などをご紹介していただきます。
【執筆・監修者紹介】山田 裕美 先生

大阪公立大学 国際基幹教育機構 高度人材育成推進センター 講師
2012年、九州大学経済学府産業マネジメント専攻(QBS)修了(MBA)。大学卒業後、IT企業に就職。退職後、Asian Institute of Technology(タイ)、ESCP-EAP
Europeにて修士修了。タイにて事業立ち上げ、本社マレーシアにてManaging
Directorを経験し、帰国後、QBSヘ入学。上海交通大学留学後、九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター(QREC)に着任し、アントレプレナーシップ教育、研究に携わる。2022年度より大阪公立大学国際基幹教育機構高度人材育成センター講師の他、高校生や小学校等も教育を実施している。
アントレプレナーシップ教育に求められること
アントレプレナーシップ教育について、ヨーロッパ、特に欧州連合(EU)では、起業家精神に必要な能力を体系的にまとめた「EntreComp(Entrepreneurship Competence Framework)」[2][3]という指針を示しています。EntreCompは、3つの大きな領域と15のコンピテンシー(能力項目)で構成されております。
以下は、EnterCompの3つの領域です。
①Ideas & Opportunities(アイデアと機会)
②Resources(資源の活用)
③Into Action(行動への移行)
| エリア | |
|---|---|
| アイデアと機会 | 機会の発見 |
| 創造性 | |
| ビジョン | |
| アイデアの評価 | |
| 倫理的・サステナブルな思考 | |
| 資源 | モチベーションと根気 |
| 自己認識と自己効力感 | |
| 財務的・経済的リテラシー | |
| 他社の動員 | |
| 資源の動員 | |
| 行動へ | 経験からの学習 |
| 他者との協働 | |
| 計画と管理 | |
| イニシアチブを取る | |
| 曖昧さ、不確実性、リスクに対処する |
「Ideas & Opportunities(アイデアと機会)」では、身の回りや社会の課題を見つけ、それを解決する方法を考える力が求められます。「Resources(資源の活用)」では、自分自身や他者の強み、道具、時間、時にはお金といった資源を効果的に使う能力を養います。そして「Into Action(行動への移行)」では、計画を立てて実行し、失敗からも学び続ける姿勢が大切とされます。これらの指針は15のコンピテンシーに細分化され、年齢や経験に合わせて「Foundation(基礎)」「Intermediate(中級)」「Advanced(上級)」の3段階、さらにレベル1から8までの習熟レベルが設定されています。これにより、各学年で育むべき能力が明確に示されています。
このEntreCompで、小学生は主に「Foundation(基礎)」レベルに位置づけられ、この段階の目標は、周囲のサポートを受けながら自分のアイデアを試すことにあります。例えば、学校生活をより楽しくするために友達と話し合ったり、自分の考えを先生や友達に伝えたり、うまくいかなくても「次はこうしよう」と挑戦と振り返りを繰り返すことが大切です。
また、アントレプレナーシップ教育を受けることで、主体性や自己効力感が高まることも確認されています。
大学生の場合、研究の例として、法政大学の田路先生らが、アメリカ・シアトル発祥の「Startup Weekend」という3日間の起業体験プログラムに参加した大学生の起業意欲の変化を調査しました。[5]心理学者Ajzenの「計画的行動理論(TPB)」を用いて、周囲の評価や起業への態度、自己効力感が起業意志にどう影響するかを分析しました。最も影響を与えたのは「起業に対する態度」であり、さらにプログラムに没頭する「フロー状態」が質の高い学習と成長につながることを明らかにしました。
この研究から得られる気づきは、単なる知識習得だけではなく、夢中になれる活動や成功体験が若者の挑戦心を大きく育てるということです。教育現場でも、仲間と協力して夢中になれるプロジェクトや小さな成功体験を積むことが、こども達の未来を切り拓く力とやる気を育むと考えられています。
心理学者ミハイ・チクセントミハイ氏が提唱した「フロー理論」は、人が何かに深く没頭し、時間を忘れるほど集中している状態を指します。彼は長年にわたり、芸術家やアスリート、科学者、また日常の中で何かに熱中する人々を調査し、共通する心理的特徴を明らかにしました。
フロー状態には、以下のような特徴があります。
・活動の目的や目標が明確である
・即時のフィードバックが得られる
・課題の難易度と自分の能力が釣り合っている
・時間の感覚が変化し、没頭している
・自己意識が薄れ、集中している
・結果よりも過程そのものが楽しく、活動自体が報酬となる
このような状態では、集中力が高まり、自分でも驚くような力を発揮できることがあります。特に「少し頑張ればできそうだ」と感じる課題への取り組みは、達成感を得やすく、学びの深化にも効果的です。
また、こうした挑戦を積み重ねることで、「自分はやればできる」という自己効力感が育まれます。研究でも、やや難易度の高い課題に取り組む“ストレッチ型”の学習が、自己効力感の向上に有効であることが示されています。
日本のこども達は、国際的に見て自己効力感や自己肯定感が相対的に低い傾向があります。そのため、日々の教育の中で「少し難しいけれど、挑戦すれば達成できる」課題を経験させることが重要だと考えられます。そして、失敗を恐れずに挑み、やり遂げる体験を重ねることで、「自分はできる」という感覚が育っていくものと思われます。
こうした教育はこども達にとって大きな力となりますが、同時に私たち大人にとっても大切な視点です。教える側の私たちも日々の実践の中で小さな挑戦を意識し、その姿をこども達に見せていくことが、良い学びのモデルとなるでしょう。
小学校での実践事例
私自身も大学で教える中で、学生たちが進路選択に迫られて慌ただしく就職活動を始める現状を見てきました。そこで、もっと早い段階からアントレプレナーシップ教育を取り入れられないかと考えていたところ、福岡県直方市の公立小学校で総合的な学習の時間を使ったアントレプレナーシップ教育の機会をいただきました。
最初は、フィンランドの小学校で行われている、レーザーカッターを使って制作したアクセサリーを販売する活動を参考にしていました。また、オンライン交流で日本の児童たちが考えたアイデアをフィンランドのこども達に発表するなど試みましたが、残念ながら時差の問題で十分な時間が確保できませんでした。さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大により対面販売が難しい状況だったため、まずはフィンランドの方々に向けた商品のプレゼンテーションを英語で行うプログラムに取り組みました。
最終的な発表では、体育館に児童全員が集まり、オンラインでフィンランドの先生方と接続して、一人ひとりが一文ずつ英語でプレゼンテーションを行いました。短い英語のフレーズではありましたが、自分のアイデアや言葉が相手に通じたという経験は、児童たちにとって大きな達成感となり、自己肯定感や学習へのモチベーションの向上にもつながりました。
新型コロナウイルス感染症の状況が落ち着いた近年では、小学校のバザーに出店することを目標に、商品アイデアの検討や試作品作り、市長への表敬訪問を行い、キャラクター使用の許可を得て値段設定から販売まで体験しています。
最初は恥ずかしがっていた児童も、最後には知らない大人に自信を持って商品を紹介し、「いらっしゃいませ」の声も廊下や隣の教室に響くほど大きくなりました。こうした成長は先生方も日々実感されていることでしょうし、そのやりがいが先生方のモチベーションにもつながっているのだと感じます。
「やってみたい!」を育てるアントレプレナーシップ教育のポイント
現在の学校教育に、EntreCompをベースにしたアントレプレナーシップ教育の考え方を取り入れることは決して難しいことではありません。特別な授業を新たに設けなくても、既存の教科や活動の中に組み込むことで実践が可能です。
たとえば、日常生活の中で自分や周囲の困りごとを見つけ、それをより良くするためのアイデアを考え、実際に試してみる――こうしたプロセスを通じて、こども達は自然と課題解決力や創造性を育んでいきます。例えば、地域の魅力を伝えるポスターや動画を作成する活動などは、調べる力、表現力、協力する力を養う絶好の機会であり、ICT活用や図工、総合的な学習の時間とも深く関わっています。
また、「誰のために役立つのか」「どうすればもっと良くなるか」といった“価値”の視点を持つことも、重要な要素です。
先生方にとっては、「起業家教育」という言葉がやや遠いものに感じられるかもしれません。しかし、アントレプレナーシップ教育とは、こども達の「やってみたい!」という思いを応援し、それを価値ある形に育てていくための指針です。
この視点を日々の授業や学校生活に取り入れることで、こども達はより主体的に学び、自分の考えを社会とつなげる力や、自ら価値を創造する力を育んでいくことができます。
ご家庭でも、こどもの「やってみたい!」という気持ちを応援し、小さな成功を一緒に喜ぶことが大切だと思われます。
「いいね」と受け入れる声がけは、こどもの発想力や行動力を引き出す大きな力になります。
子育ては、思い通りにいかないことも多く、つい叱ってしまったり、自己嫌悪に陥ったりすることもあるかもしれません。そうした中でも、こどもの「やりたい」という気持ちに寄り添い、実際に挑戦させてあげることは、こどもの成長を支える大きな一歩になります。
時には、大人自身もこどもの頃の気持ちを思い出し、一緒に楽しむ時間を持てると理想的ですね。
私たち大人の方が、経験や知識がある分、固定観念にとらわれたり、新しいことへの一歩をためらってしまったりすることもあります。
しかし、アントレプレナーシップ(起業家精神)は、決してビジネスを始めるためだけのものではありません。身のまわりの課題に気づき、誰かのために工夫したり、行動したりすることも、立派な実践です。
こうした視点は、すでに日常の中で自然と行われているかもしれません。こども達の「やってみたい!」を温かく見守り、支えていくことが、未来の力を育てていくことにつながります。
Think out of the box
希望に満ちている世の中にできるよう、これからもアントレプレナーシップ教育を実践出来ればと思います。
キッザニアで育むアントレプレナーシップ
実践編では、教育現場でどのようにアントレプレナーシップが育まれているのか、小学校における実践例をご紹介しました。こども達が自ら考え、挑戦し、仲間と協力しながら成長していく姿は、未来を切り拓く「生きる力」が醸成されるプロセスといえるでしょう。
キッザニアの各パビリオンもまた、こども達の「生きる力」を醸成するための場のひとつです。ここでは、働くというロールプレイを通じて企業活動や社会の課題に触れ、楽しみながら実践的な力を育む工夫がほどこされています。
例えば、キッザニア東京の「総合商社」パビリオンでは、日本の優れた製品を海外に紹介し、販売する商社パーソンの仕事に挑戦できます。担当商品の知識を深め、海外のお客様に英語でプレゼンテーションを行う中で、自ら考え行動する力、新しい価値を生み出す創造力、そして困難を乗り越えるやり抜く力といった、アントレプレナーシップの精神を育むことにつながるでしょう。また、こども達が商社の仕事を体験することで、英語への関心を高め、国際的な視野と交渉力・プレゼンテーション力を育んでほしいというパートナー企業の想いが込められています。

また、キッザニア福岡の「ビジネスイノベーションセンター」パビリオンでは、最新の技術を使って社会課題の解決に挑む体験ができます。こども達は環境問題や資源循環など、現代社会のテーマに触れながら、自らアイデアを考え、行動に移す楽しさを学びます。このパビリオンには、未来を見据え、こども達の創造力や挑戦する心を育みたいというパートナー企業の温かな想いが散りばめられています。
このようにパビリオンに協力する企業の想いは、こども達の経験を通じて「生きる力」となり、キッザニアを支えています。そして、そこでこども達が自分の可能性に気づき、社会とのつながりを感じることが、未来の起業家精神=アントレプレナーシップの土台となっていくのではないでしょうか。
アントレプレナーシップは、身近な環境の中で、挑戦し続ける姿勢や、自分らしく考え行動する力として、誰もが育てていけるものだと考えらえます。
キッザニアはこれからも、教育現場やこうした体験の場と連携しながら、こども達の「生きる力」を育む取り組みが広がっていくことを願っています。
資料ダウンロード
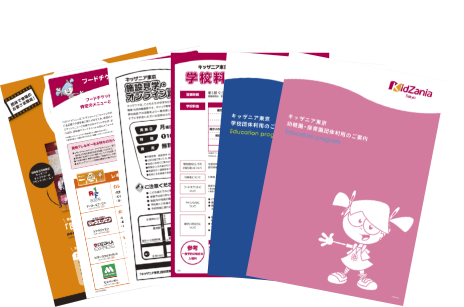
- 東京都「小中学生起業家育成プログラム」
- EntreComp: a practical guide, easing the access to entrepreneurship
- Competence areas and learning progress
- 経済産業省 アントレ教育ガイド(アントレコンプ)
- 起業家体験プログラムにおける起業意思と諸要因の関係-Startup Weekendプログラム参加者を対象にした分析方法の探索-秋庭太、田路則子、八名和夫、林永周、浅川希洋志
フロー経験と起業マインド ―3日間のStartup Weekendは起業マインドを高めるか―
田路則子; 浅川 希洋志; 林 永周; 山田 裕美
日本ベンチャー学会, 2020年12月05日, 日本ベンチャー学会

